プロの楽器奏者の方や音楽教室に通っていて発表会に参加したことある方であれば、楽器奏者が本番中、常に緊張感を持って演奏していますよね。本番や練習中、楽器によって異なりますが指や腕などの特定の筋肉や関節に負担がかかります。
しかし、あまり知られていないのは、楽器奏者がアスリートと同じように、からだのケアが必要なことです。
今回は、楽器奏者のからだケアの重要性について解説します。
楽器演奏は、フルートやバイオリンなど日常生活の姿勢から逸脱した演奏姿勢となる楽器が多く、長時間にわたり演奏したり、同じポーズを続けることで負担がかかります。また、強く奏でる場合には、腕や手首、指先に大きな負荷がかかります。こうした負荷が長期間にわたって続くと、慢性的な痛みや怪我を引き起こすことがあります。
しかし、全身運動ではないため演奏に慣れてしまうと指の疲れを疲労と感じにくくなること、練習中のミスや指の動かない原因が練習不足と勘違いしてしまう人も多く、オーバーワークを起こしてしまい症状が悪化させるケースも少なくありません。

楽器奏者がアスリートと呼ばれるのは、なぜでしょうか?それは、楽器演奏に大量のエネルギーを必要とするのが一つの理由です。2時間のピアノ練習が45分のジョギングと同程度のエネルギーが消費されるとの研究もあります。
 楽器奏者はアスリート?!アスリートに例えられるのはなぜか、からだのケア必要性も含めて解説!
楽器奏者はアスリート?!アスリートに例えられるのはなぜか、からだのケア必要性も含めて解説!
また楽器演奏は、指の動きなど高度な身体的コントロールを必要とし、緊張感がかかる演奏会などの本番で楽器奏者がアスリートと同じようなプレッシャーを感じながら演奏します。
スポーツのような全身運動ではないため疲労を感じにくいこと、演奏に慣れてしまうと疲労を疲労と感じる方が少なくなること、指や腕の疲労感が良くなっても指導受けている先生から「休めば治るはず」と言われる方が多く、休めば治ると思われがちであることも原因です。
楽器奏者は、演奏することで肩から指までからだに負荷がかかるため、からだのケアが必要です。特に指に関わる筋肉や関節は、自分が思っている以上に硬くなっている人が多いです。
違和感や張りを感じて音楽教室の先生に相談しても先生が経験していないと「休めば治る」と言われがちですが、安静にしていて疲労は取れますが、硬くなった筋肉の状態は回復しません。演奏中にミスが多い方や指の動きにくさを感じる方は、筋肉が必要以上に硬くなり柔軟性が低下しています。
からだのケアとして、ストレッチや運動、効率のいい腕の動きや姿勢を保つためのボディマッピングなどを行うことが大事です。また、筋肉や関節の柔軟性がセルフケアでも改善が見られない場合は、専門家に相談して施術や治療を受けましょう。

からだのケアは、楽器奏者がより良い演奏を行うためにも重要です。音を出すのは楽器ですが、奏でるのは奏者本人です。張りや痛みなどの不調無く身体のコンディションが整っていれば、演奏もよりスムーズになり、高いパフォーマンスを発揮することができます。
また、からだに痛みや怪我がある場合、演奏中の集中力が散漫になったり、演奏ミスが増えることにつながります。これは、楽器奏者にとって非常にストレスフルな状況であり、楽器奏者としての自信を喪失することにもつながります。最悪の場合、フォーカルジストニアやうつ病などの治るまでに時間がかかる病気になってしまいます。
楽器奏者は、演奏や練習に多くの時間を費やすため、本番に近づけば近づくほど演奏に集中するためからだのケアを怠ることがあります。ですが、練習を積む分だけアフターケアは重要なので意識しないといけません。
一度不調を経験している人は、疲労に伴う腕の張りなどを感じやすい人も多くなるため不調をぶり返すことがあるので注意が必要です。

整体サロンHarmoniaでは、楽器奏者に起こりやすい肩から指における痛みや張り、腰痛、首の痛みといったパフォーマンスに影響を及ぼす不調を改善へ導く音楽家特化の整体『楽器奏者のコンディショニング』を行っています。
解剖学・運動学に基づいた身体の使い方に整える施術やボディワークを行い、その人のパフォーマンスを高める身体へ導きます。
現在、フルート・バイオリン・チェロ・ギター・ピアノ・三味線などの楽器を演奏するプロからアマチュアの方までご利用いただいています。本番前の身体のメンテナンス、効率のいい身体の使い方の習得などぜひご相談ください。
 楽器奏者のコンディショニング
楽器奏者のコンディショニング
楽器奏者は、アスリートと同じように、からだのケアが必要です。からだに負荷がかかる状態で演奏や練習を繰り返すことで痛みが悪化したり怪我が生じる可能性があります。からだのケアを怠ると、演奏の質や量が低下するだけでなく、楽器奏者自身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。
楽器奏者は、定期的にストレッチや運動、正しい姿勢の維持など、からだのケアを行うことで、より良い演奏を行うことができます。また、からだに負荷が抜けない場合には、施術を受けるなど専門家に相談することも方法です。からだのケアは、楽器奏者がより良い演奏を行うために欠かせません。
Harmoniaは、楽器奏者のコンディショニングを行っているので、演奏中に感じる不調がありましたらHarmoniaにご相談ください。
整体サロンHarmonia(ハルモニア)は完全予約制です。以下の予約フォーム、LINE、お電話のいずれかでご予約ください。
サービス選択・スタッフ選択・ご利用希望日時をそれぞれ選んでいただき、詳細にどんな不調でお悩みか簡単にご記入ください。
※予約フォームは24時間受け付けております。(時間帯により予約確定は翌日になります。)
※オンラインでの楽器奏者のコンディショニング相談に関しては、予約フォームあるいはLINE予約よりご予約ください。
 熊谷市の整体サロンHarmonia
熊谷市の整体サロンHarmonia 

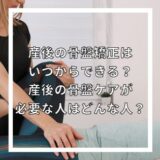
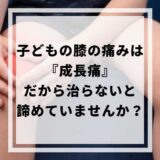
[…] 以前投稿したブログ記事「音楽家もアスリート!」にて、全身運動としての動きは少ないものの、指や腕への負担は大きく、日々のケアが必要であることをご紹介しました。 […]